こころにはかたちがある
そのかたちがゆがむと
いくら幸せがやってきても
それを幸せとかんじることが
できない
まず、肩の力をぬき
こころを自由に
ときはなしてみる
こころのかたちは
自らが創り出すもの

|
What is TFT TOKYO?
私たちの基本...それは触覚です。
エステ・スクール・化粧品・etc
触覚?芸術?科学?
きっと、すべて美容には関係ないようにみえると思います。
私たちにとってすべての基本はファセテラピー、つまり、マッサージ
化粧品もスクールも何をとってもすべてはファセテラピーにあります。
私たちの活動のすべての中心は
触覚
にあるのです。
私たちは触覚に関する芸術・科学的研究と共に、かかる分野の振興事業を行っています。
それは
美容に限らず、触覚こそ私たちにとって最も重要な感覚であると考えているからです。
子供はなぜさわりたがるのだろう?
産まれたばかりの赤ちゃんは目がよく見えません.言葉もわかりません.だから触ります.触るとはいきることに繋がった大切な感覚.だから子供は触りたいのではないでしょうか.ものを触る子供の手はこころに繋がっているから………
”触覚をきく”~ hear と
listen
hear:vt. (heard
) 聞く; …が聞こえる, 耳にする
listen vi. 傾聴する,
聞く; 耳を澄ます
耳には音楽があり,そして,目には絵画があります.では,触覚にはなにがあるでしょう?
触覚は能動的です.触覚は観賞して作品に”こころをうごかしてもらう”ことができません.自分で”さわりにいく”そして”こころをうごかす”必要があるのです...触覚は聞こえてこないし,見えてもこないのですから.ぴちぴち
ちゃっぷちゃっぷ らんらんらん~ 子供達にとって水たまりは触覚を刺激する”作品”です.なんてワクワクしたでしょう.子供達は”触覚をきいている”のです.なぜ,わたしたちは”触覚をきく”必要があるのでしょう?それは,こころは触覚に深く繋がっているからです.ですから,触覚を通して自分の”こころ”にほんの少し触れることができるのかもしれません. |
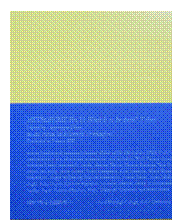 |
DOCUMENTA 12の公式マガジン Metronome に参加(寄稿と作品)
Metronome Think-Tank Tokyo
in collaboration with documenta 12
magazines 16th and 17th September 2006, Mori Art Museum Tokyo
Curated by Clémentine
Deliss
Hosted by Mori Art Museum, Tokyo
Coordinated by Arts Initiative Tokyo
& Nozomi, Edimburgh College of Art and School of Fine Art, University
of Dundee
Supported by Academy Hills, Tokyo;
The University of Edimburgh; School of Fine Art, University of Dundee;
Scottish Arts Council; Culturesfrance
In September 2006, Metronome held
a Think Tank in Tokyo hosted by the Mori Art Museum. The two-day meeting
behind closed doors brought together 65 leading artists, architects, designers,
scientists and educators from major cities in Japan (Tokyo, Nagoya, Kyoto,
Osaka, Hiroshima, Yamaguchi) and worldwide (Edinburgh, Paris, Antwerp,
Berlin, Athens, Stockholm, Portland, Oregon, New York, Melbourne, Sydney,
Beijing). It addressed the following questions :
Can knowledge be mobile? What forms
of knowledge travel, who shifts them from one place to another, and how
does their content after? What forms of knowledge do not travel or translate
and why? Why are artists coming back to the question of education? Under
what conditions can art colleges and universities generate autonomous
dynamics of research and production? How do we assess the artist's articulation
of a combination of activities that include private gallery shows, large-scale
global events and activist education? How do we articulate differences
in concepts of research and in the methods of acquiring knowledge? Moving
schools: is this classical romanticism (the peripatetic thinker and artist)
and if not, what is required to make itinerant academies into a reality?
Metronome No.11
What is to be done? Tokyo
Tokyo, 2007
Edited by Clementine Deliss
Special edition for documenta 12
magazines
In its tradition of adopting an existing
organ as a model for its publications, Metronome No. 11 has been influenced
by two publications. First, the Japanese propaganda magazine Front produced
just after the bombing of Pearl Harbour in over sixteen languages and
built up nearly entirely of image sequences printed in monochrome blue
or brown ink. Secondly, Sleeping Beauty Art and Education, an artwork
by Japanese artist, Masato Nakamura, which provides the contemporary reference.
This Japanese/English bi-lingual issue of Metronome presents the original
images, texts and debates from the Metronome Think Tank held in Tokyo
last autumn, and produced in collaboration with documenta 12 magazine.
Covering questions on contemporary art, education, translation and mobility.
In addition, each participant chose four images that represent Future
Faculties of Knowledge relevant to future art education in whatever form. |
 |
鈴木理絵子 (Haptica project):
Tokyo Face Therapie(TFT サロン&スクール-東京・名古屋・京都)代表.
多彩な触感覚を喚起させるマッサージ(Face Therapie)の創造と提案、触覚を重視したコスメティックの開発と展開。我々の触感覚の“おやつ”になるようなアート作品の企画・デザイン・制作等(haptica
haptica, ファッション&雑貨)、“触覚”を軸として多方面で活動を展開している。
Rieko Suzuki (Haptica project); the
representative of Tokyo Face Therapie and co-organizer of Haptica Project.
She originated and has proposed a novel way of massaging for beauty that
can evoke the wide varieties of sense of touching (Face Therapie salon
& school .. tokyo, nagoya and kyoto). She has also proposed and design
objet d’art and products that evokes our sense of touching (haptica haptico
fashion and haptic goods).
鈴木泰博 (Haptica project)
サイエンス&アート:複雑系・ナチュラルコンピューティング研究の一環として触覚の科学、サイエンティフィックビジュアライゼーションに興味を持つ。Haptica
project; 触覚を介したヒトとヒトの相互作用に関するアート&サイエンスプロジェクト代表(名古屋大学大学院情報科学研究科准教授 名古屋市立大学芸術工学部非常勤講師 人工知能学会ナチュラルコンピューティング研究会代表発起人・主査 情報処理学会 計測自動制御学会委員)。
Yasuhiro Suzuki (Haptica project);
Science & Art: His scientific interests are mainly on Complexity (the
origin of life, systems biology, eco-systems), Natural Computing (artificial
chemistry, novel framework for discrete dynamical systems, etc) and also
interested in science of touching and scientific visualization. He is
the founder and organizer of haptica project. (Associate Professor, Dept.
of Complex Systems Sci, Graduate School of Infromation Sci. Nagoya University,
lecture (part-time) Dept. of Art and Eng. Nagoya City University, a founder
and the leader of the natural computing research group of Japanese Society
of Artificial Intelligence, committee member of Information Processing
Society Japan). |

|
活動歴
2004年 12月 東京 TFTサロン body workshop
2005年 3月 京都 法然院 body workshop
2005年 12月 京都 法然院 body workshop
2006年 3月 名古屋大学(感覚設計国際シンポジウム招待ワークショップ)
2006年 9月 Collex Speak For展示(東京・代官山)
2006年 9月 地中海美学国際会議(スロベニア) 研究発表&論文出版(地中海美学誌)
2006年 9月 Metronome Thinktank Tokyo参加(森美術館)
2006年 11月 名古屋大学(感覚設計国際シンポジウム招待ワークショップ)
2007年 1月 エキゾチック-Media Selectの感覚ツア-
インスタレーション&ワークショップ(愛知県児童総合センタ)
2007年 2月 本郷小学校 特別授業bodyworkshop(東京都文京区)
2007年 7月 Documenta 12 (Metronome
11, documenta 12 official magazine)
寄稿とグラフィック作品
2007年 12月 名古屋大学(感覚設計国際シンポジウム招待ワークショップ)
Dec. 2004 Body workshop, TFT salon,
Tokyo
Mar. 2005. Body workshop and exhibition,
Hohnenin Temple, Kyoto
Dec. 2005 Body workshop and exhibition,
Hohnenin Temple, Kyoto
Mar. 2006 Body workshop (invited),
International Symposium on Multi-sensorial design
Sep. 2006 exhibition, Collex Speak
For, Daikanyama, Tokyo
Nov. 2006 Body workshop (invited),
International Symposium on Multi-sensorial design |

